とうとうGWが終わってしまい、7月21日海の日まで祝日が無いことで気分がブルーになっている方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
足掛け11連休も可能だと言われた2025年GWの間にも、世界はトランプ関税に振り回され続け、個人的には「そろそろお腹一杯!」気味ですが、日本以外の先進国では相当なアンチ・トランプの風潮が強まっている模様で、
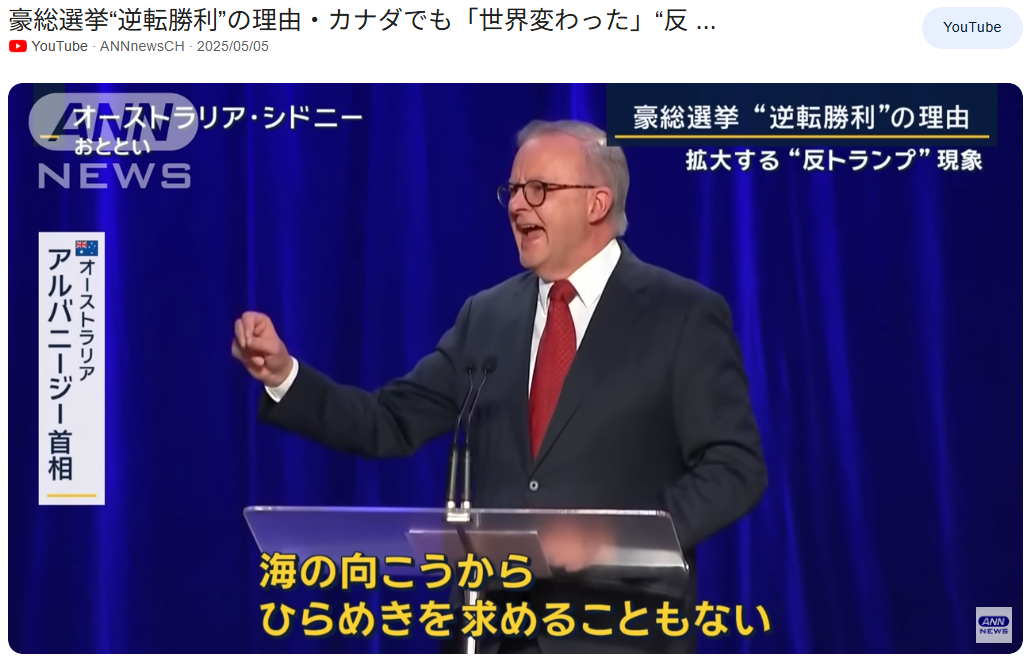
※YouTube版ANNnewsCHから豪州アルバニージー首相再選を伝える5月5日動画記事をキャプチャー
4月28日のカナダ議会選挙や5月3日のオーストラリア総選挙では、じり貧だった与党がアンチを前面に押し出したことで、逆転大勝利を収めるなど、世界の様々なバランスがトランプ氏によって大きく変革しようとしています。
かねてから常識とされてきたあらゆる慣行やシステムの再構築はトランプ氏の目的の一つだったと記憶しており、理不尽とも言える外交姿勢の急転換で世界が動き出したのは事実のようです。
結果的に、生みの苦しみから新たなシステムが構築され、少なくとも自由主義国家がある程度まとまるのか、一層の保護主義が蔓延してしまうのかは予断を許さないものの、
少なくとも基軸通貨たるドルの母国アメリカには自由主義国家の間だけでもまとめ上げられるようなリーダーシップを発揮する義務があるように思え、それ自体をないがしろにする様であれば、ドルの立場は益々弱体化するのは必至だと思われ、アンチの輪が広がり過ぎないことを祈るばかりです。
ところで目線を国内に移すと、石破内閣はトランプ関税対策で夜も眠れない日々が続いているだろうことは察しがつきますが、新年度予算が通過したからといって、先伸ばしてきた様々な内政課題は山積しており、それらの進捗状況が見えてこないようでは、夏の参院選結果が危ぶまれます。
個人的には決して自民党を擁護している訳ではありませんが、トランプという不確実性が新たに加わった複雑な政権運営を可能にするのは現状維持しかないとも感じており、選挙結果を受けて万が一でも内閣改造などによりゼロスタートとなるような担当大臣が出てしまっては、日本全体のダメージになりかねないと危惧しています。
そうならないためにも、夏までの間に内政面で日本国民に訴求できる成果を見せていく必要があり、例えば今回のタイトルにも挙げたように、物価対策や果ては経済的困窮者支援策などについて定期的な報告があっても良いと思うのです。
103万円の壁は、段階と時限付きの160万円で合意があり、どちらかというと経済的困窮者対策的な側面が強いものの、かろうじて新年度予算に間に合いましたが、物価対策に向けた給付金は結局破談となり今も宙に浮いた状態ですね。
国民に対して一律な給付金の形態をとらなかった決断は一応は拍手を送りたいところですが、一時的にしろ何故そのような発想になったのか理解に苦しむところであり、限りがある財源だからこそ効果的な対策が必要ならば、安易な給付金はあり得なかったところです。
物価高は国民全体に同様にのしかかる困難ではあるため、物価高対策は急務だと思いますが、消費税率の見直しがそれほど難しいのか疑問です。
難しい根拠として与党からは、税収の減額分を補う財源を問題視する発言があったと記憶していますが、例えば高騰を続けるお米で考えると、僅か1年前には5キロ2000円、そして現在は4000円だとして、消費税額8%はそれぞれ160円と320円ですから、政府は何もしなくても160円の税収増となっており、1年前の消費税額だけを見れば現在価格4000円の4%と同じことになります。
全体としての物価高は今のところお米ほどではないにしても、一般的に言うところの「生産者」が値上げすると政府の税収も増える消費税という仕組みは、インフレ時代にとって非常に不合理な仕組みであることは間違いなく特に、値上げしても誰もがさほどの増益にならないコスト上昇型のインフレでさえも、政府の税収だけは自動的に増えるのです。
野党の誰かが「取り過ぎた税金を国民に返せ!」と言っていたと記憶していますが、軽減税率対象分だけでも直ちに3%や5%に引き下げても、与党が言うほど大きな問題にはならないのではないかと思います。
もしかするとインフレ増税を見込んでの予算だったとすれば、消費税率の引き下げは確かに難しいかも知れませんし、一時的にしても僅かな一律給付金という発想に至った背景だったのかも知れないと疑いたくもなりますね。
また、物価対策としてガソリンの暫定税率(現在の特例税率)の廃止という議論もありますが、自動車を持たない国民や持てない国民には何のメリットも無く、廃止はそれこそ財源の圧迫につながる気がします。
それならば、自動車や船舶がどうしても必要な方々や、運輸関係に限って一時的でも減税し、それがコストの低下につながってインフレ圧力全体の低減に役立つ方が全国民に対してフェアですし、その効果に期待する方が夢があると思いますが、皆さんはどう思われますか?
さてお仕舞いに、
トランプ氏が姿勢を崩さない限り、アメリカ離れはそれなりに継続しそうです。
この波はドル安という形で表れている訳ですが、日本の輸出企業にとっては歓迎できない方向性ではあるものの一方では、関税対策としてアメリカ本土への設備投資を本当に行う場合、ドル安は逆に追い風になりますから、円高だからといって単純に輸出企業の株を売るという発想には、もう一捻りが必要になっていくかもしれません。
何れにしても、WTIは60ドル前後まで下落している以上は、円安が日本のコストインフレの一大要因であるのは確かです。
あとは実際にコストが下がった際に、本当にコスト減分の値下げがあり得るかどうか、難しいと言われるインフレ対策はそこまでがゴールになるでしょう。
浅野 敏郎